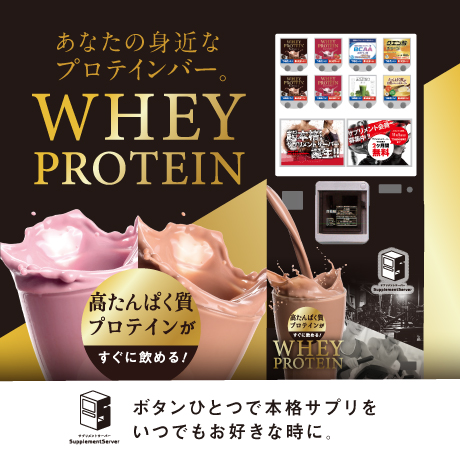2013年6月19日に開催された株式会社星野リゾート 星野佳路氏によるFIA特別セミナーレポートです
2013年6月19日(水)、東京有明ベイワシントンホテルにて、FIA特別セミナーが開催された。講師はリゾート施設の再生事業ほか、そのサービスレベルの高さから国内外から多くの人を惹き付ける温泉旅館の運営を手掛ける株式会社星野リゾート(以下、星野リゾート)代表取締役社長 星野佳路氏。リピート客も多く生む星野リゾートとはどのような会社なのか。同社のユニークな取り組みについての講演内容を抜粋する。
星野氏が社長に就任したのは1991年。当時は’87年に施行されたリゾートにより、業界に次々と大手企業が参入し、競争が激化していた。そのなかで同氏は、参入する多くの企業が「開発」などには積極的な反面、地味なイメージの「運営」にはそれほど興味をもっていないことを感じていた。しかし、地味ながら運営は、その善し悪しが売り上げに大きな影響をおよぼす重要なものである。そこで星野氏は、他社との差別化も含め、社長就任早々「運営がどこよりもうまい企業になる」を会社のビジョンに決定。現在も変わらずそのビジョンに
向けて努力を続けている。
星野氏が社長に就任後、10年間は軽井沢内での案件に携わるに止まっていたが、’01年に初めて受けた軽井沢外からの再生案件を成功に導いたことが転機となり、同社には次々と依頼が舞い込むようになる。そこで問題になったのが人材不足だ。案件が増えれば当然人材が不足する。社内からは「人材がいないのに、やみくもに施設数を増やすべきではない」という意見も挙がったという。しかし星野氏は「事業を拡大する局面において、『人・金・モノ』すべてがきちんと揃っているなどということはほとんどない。欠けている要素は今あるものを工夫して乗り切ろう」と伝え、人材の能力を企業の成長速度に合わせる方針をとる。このようにして、さまざまな不足事項を工夫によって克服していった結果、ユニークな社内制度ができあがったのだという。そこで、星野氏が挙げる5つのキーワードをもとに、星野氏の成功へのビジョンと、そのような制度が生まれた背景などを紹介したい。
Keyword1. ビジョンと価値観の共有
’84~’86年にアメリカの大学院にて学んでいた星野氏。そこである教授が述べた言葉が、現在でも同氏のビジネスマインドに影響を与えているという。それは「経営者、マネージャー、チームリーダーなどが最初にすべきことは、そのチームのビジョンと価値観を明確にして、それを共有すること」というものである。そもそもビジョンとは、企業ならば「将来はこういう企業になりたい」という将来の姿を描くことである。しかし、
ランキング
- 1. 法務関係フィットネスクラブで使用する音楽の使用料 の支払いについて
- 2. 法務関係年一括払い契約の途中退会について
- 3. FIA_NEWSFIA-NEWS2023-11月号
- 4. 会員継続FIA全国カラダ年齢測定ーフィットネス体力テストー【レポート4】
- 5. フィットネス・プログラミング【海外フィットネス関連情報】アクアティクス、プール、ハイドロセラピーに関する14の ベストプラクティス・ガイドライン
運営事務局おすすめ
- 法務関係国民生活センター発表「スポーツジム等の契約トラブルにあわないために」
- 経営戦略と業界動向厚生労働省 運動ガイド2023(案)
- 法務関係【事例共有】消費者団体からの申し入れ・問い合わせ(会員規約関連)
- 会員継続エクササイズは小児癌の生存者にとって非常に有効(2013/7/1)